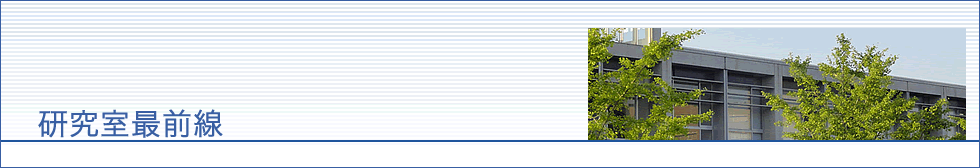
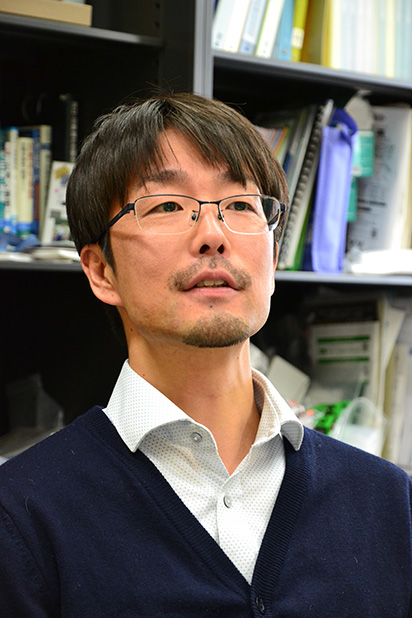
地球上にはいまだ未知の生物が数多く存在する。それらの機能、役割は不明であり、そもそも名前すら与えられていない。世界中が大混乱に陥った新型コロナのような感染症を引き起こすかもしれない。北九州市立大学国際環境工学部生命工学科の柳川勝紀准教授は、自然環境に存在する難培養性微生物の解明を目指している。地底や深海など極限環境下にある微生物の謎を解くことで、命のまた種の起源に迫ろうとしているのだ。
Q研究内容を教えて下さい。
柳川 自然環境の微生物の生きざまを知ることが研究内容です。変わった環境、特に極限環境を対象としています。極限環境というのは高温、高水圧の深海、地下数キロメートルの地下圏のような人間基準ではとうてい生きられない環境を指しますが、こういう場所からも微生物は大量に見つかります。ただその多くは難培養性で、代謝活動も何を食べているのかも不明です。このため宇宙における暗黒物質にちなんで「微生物ダークマター」と呼ばれています。研究室ではこの極限環境の微生物生態系を対象にしています。
Q研究を始めたきっかけを教えて下さい。
柳川 東京理科大学時代に所属した研究室では免疫・アレルギーに関する研究に従事しましたが、のめり込むことができませんでした。高校時代の恩師が生物教師で楽しく授業を受けた思い出もあり、フィールドを重視する今の研究に変更しました。もともと生命の起源を知りたいという思いがありました。
Q深海探査船にも乗船しています。
柳川 深海調査のためフランスやドイツの調査船に乗船した経験や、日本が誇る深部掘削船「ちきゅう」や、潜水艇「しんかい6500」による調査にも参加しました。海底温泉に含まれる微生物を採取するのが目的です。「しんかい6500」では水深5000メートルの海底に降りて400℃を超す超高温熱水を採取しましたが、さすがにこの時は緊張しました。往復9時間の潜行でしたが、真っ暗な海底でも発光するプランクトンを目にするなど貴重な経験となりました。微生物には次世代エネルギーとして期待されるメタンハイドレートや、希少金属を含む海底熱水鉱床といった海底資源の成因に大きな影響を与えることが分かっているので、この要因などを研究しています。
Q研究成果が社会に、地域にどのような影響を及ぼすとお考えですか。
柳川 極限環境を扱うことで、複雑な微生物の活動をシンプルに解釈することができ、生命の本質に迫ることができると考えています。有用な微生物の働きにフォーカスして社会に還元したいと思っています。微生物によるメタン生産などはその好例だと考えます。以前、100℃近い地熱地帯にも未知の微生物が生息していることを見つけました。ゲノムの大きさが異常に小さく、特殊な生き方をしていると考えています。また、花こう岩帯の地下深部を調査したときは電子の授受を介してエネルギーを獲得する微生物を見つけました。この発見が将来微生物燃料電池の開発につながる可能性があります。私の研究はいますぐに成果につながるものではありませんが、社会に還元できる真のイノベーションは一見分からないような研究から生まれています。私もそれを信じて研究を続けていきます。
Q活動を北九州市や学研都市で続ける意義をどうお考えですか。また課題などもお聞かせ下さい。
柳川 北九州市立大学は分野横断的な研究を実行しやすい環境だと感じています。また北九州市は公害を克服した歴史から環境への意識が強く、これも環境・生態学研究を進めるのに適した土台があると感じています。都市と自然がバランスよく調和しているのも強みですのでそれらをうまく活用すればまだまだ発展すると感じています。学研都市の認知度向上には私自身も貢献したいと思っています。個人の研究ではバイオインフォマティクスを使って膨大なデータを適切にさばく必要性を感じています。流行に左右されず、地道に研究を進める継続性も重要だと考えています。私の研究室は微生物のDNA解析がメインですが、温泉がある大分県や熊本県のフィールドにもよく出かけ、研究のかたわら温泉を楽しんでいます。サンプル採取後はすぐに大学に帰る必要がありますので、もっぱら足湯ばかりですが。学生には外に出て自由に研究しようと訴えています。

研究者(研究室)詳細情報: https://www.kitakyu-u.ac.jp/env/faculty/d-life/introduction/katsunori-yanagawa.html